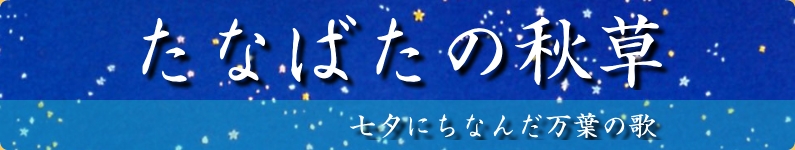中国の七夕伝説に基づき、日本でも古くから七夕の歌をよむ宴が催されていました。『万葉集』には第一〇巻に九八首の七夕歌がよまれているのをはじめ、巻八、巻九その他も合わせると、計一三二首がよまれています。
また、七夕の宴席でうたわれた歌には、「秋の七草」を題材にとったものも多くあり、野草の可憐な美しさや香りに、人恋しさがうたい合わされています。ここでは、市内在住で福岡女学院大学の東茂見教授に寄稿いただき、『万葉集』に収められている七夕歌についてみていきたいと思います。
秋の野に咲きたる花を指折(およびを)りかき数(かぞ)ふれば七草(ななくさ)の花
その一 (巻八、一五三七)
萩の花尾花葛花撫子(をばなくずはななでしこ)が花女郎花(をみなへし)また藤袴朝顔(ふじばかまあさがほ)が花
その二 (巻八、一五三八)
秋の戸外に出て、咲きみだれる花のひとつひとつを、指をおりつつ数えてみると、咲き競うように七種類の秋草が、花ひらいているではないか。萩、尾花(すすき)、葛、撫子、女郎花、藤袴、朝顔(今にいう桔梗)の花があり、きびしい夏も過ぎ去り、おだやかになった陽ざしのもと、おとずれた秋をそれぞれに飾っている。まるで数(かぞ)え歌(うた)のようでもあり、リズミカルで洒脱(しゃだつ)な感じのする歌だが、原野を彩(いろど)る七草(ななくさ)の秋草で、一首すべてを埋めつくしてうたわれるこの歌は、四五〇〇首ほどの歌をおさめる『万葉集』のなかでも、とりわけ異色な秋草の歌といえるだろう。
春の七草と同じように、秋の季節を飾る草花から七種類だけをえらんでいるのも面白いが、さらに面白く思うのは、これらの歌がどうやら七月七日の七夕の宴席でうたわれたらしいからだ。ここには「七」というカルデアの知識が、じつに見事にいかされている。そして、歌の下に記された「その一」や「その二」は、歌唱にともなって演奏された、奏楽(そうがく)の種類の違いを示しているらしい。一説によると「その一」は中国から伝えられた唐楽(からがく)、「その二」は朝鮮半島から伝えられた高麗楽(こまがく)だという。そうすると、冒頭にかかげた歌は異国の音律にのせて美しく唱(うた)われたのであって、七夕の宴のエキゾチックな催しに、まことにふさわしい二首だったことになる。宴席の場で唱(うた)ったのは、おそらく美声の歌姫たちだったろうから、宴にあつまった万葉人は、花群(はなむら)となって咲く秋草につつまれながら、海を越えたはるかな異国まで、思いをはせたにちがいない。
「秋野の花」の歌を創作したのは山上憶良という人物である。彼は朝鮮にあった百済の国が滅亡した後に、母の腕にだかれて日本にやってきた(四歳)渡来人だといわれている。彼が歴史の光のあたる場所に、はじめて登場してくるのは四十歳を越えてからで、大宝元年(七〇一年)遣唐使の一員として当時大唐帝国の都だった長安に渡っている。その後、伯耆(ほうき)の国守となり、東宮侍講(皇太子の個人教授)の一人として活躍もし、晩年には大宰府近くに庁舎があった筑前の国守として赴任し(六七歳)、四年あまりの歳月を筑紫で暮らしている。
憶良というと、すぐに思い出されるのは、次のような歌だろうか。
銀(しろがね)も金(くがね)も玉もなにせむに優れる宝子に及(し)かめやも
(巻五、八〇三)
これは「子らを思ふ歌」と題される作品で、長歌では、瓜を食べるとこどもが思われるし、栗を食べるとなおのこと愛(いと)しく思われる。いったいどのような緑と絆(きずな)でわたしのこどもとして生まれあわせたものなのか、目の先に面影がちらついて安眠させてくれないとうたい、喜びにつけ悩みにつけ、誰しも思わずにはいられない親子の宿縁(しゅくえん)の深さをうたっている。「銀も金も…」は、そうした長歌に付してうたわれた反歌である。金も銀も玉も(これらを総称して七宝(しちほう)という)こどもという存在には及ぶものなどありはしないとは、いかにも大仰なうたいぶりだが、こどもに執着してやまない親の愚(おろ)かさを、そのコミカルな調子でうたいきっている。面白うてやがて悲しき、そんな親の愛情のさまをうたった。
ところでこの憶良は、冒頭にあげた「秋野の花」の歌のほかにもたくさんの七夕の歌をうたう歌人でもあった。神亀元年(七二四年)の七夕には、左大臣である長屋王(ながやおう)の文芸サロンに招待されて、
ひさかたの天(あま)の川瀬に船浮(う)けて今宵(こよひ)か君が我許来(わがりき)まさむ
(巻八、一五一九)
の一首をうたっている。これは牽牛のおとずれを待つ、織女の立場でうたったもので、七夕の宵に、再会するはずの時刻が近づくにつれて、いやがうえにも高ぶってくる期待感と緊張とにあふれている。憶良がこの歌を披露(ひろう)した宴の主催者長屋王は、のちに国家を傾けようと謀った罪(実は無罪だったが)で糾問(きゅうもん)され、自殺して果(は)てるという悲運の人物だが、中国ふう文芸サロンを主催しており、当時の漢詩を収める詩集の『懐風藻(かいふうそう)』には、新羅(しらぎ)から来日した使者を迎えて催された宴席の漢詩が数多く残され、七夕の漢詩もまた留められている。
憶良は日中韓の三ヶ国語とその文芸に通じていたと思われるから、神亀元年の七夕の宴では、漢詩ではなくむしろ倭歌(やまとうた)でもって七夕のロマンスをよむことを、周囲から請(こ)われたのだろう。
さて、憶良の歌によると、牽牛と織女の出会いは、牽牛が船で河をわたって会いにいくことになっている。とはいえ、ひろく知られているのは、鵲(かささぎ)が翼(つばさ)をひろげて橋となり、織女がその橋をわたるという伝説だろう。これは中国から伝わったもので、中国では織女が船に乗って渡るとも伝えられていた。
鵲の橋をうたうのは、同じ万葉の歌人大伴家持で、
鵲の渡せる橋におく霜の白きを見れば夜(よ)ぞふけにける
(新古今集 冬)
とうたっているが、『万葉集』にこの歌がないことから、たぶん家持が実際に作ったのではなく、後の平安時代に家持の作となって伝えられたのだろう。『新古今集(しんこきんしゅう)』のなかの歌というよりも、どちらかといえば『百人一首』の六番歌として有名な歌である。
もちろん、家持も七夕の歌を創作している。いまは一首だけをあげてみよう。
織女(たなばた)し船乗りすらし真澄鏡清(まそかがみきよ)き月夜(つくよ)に雲立ち渡る
(巻十七、三九〇〇)
清らかな月夜に雲がかかってしまったと、はるかにのぞむ天上の雲を、織り姫の船出の水しぶきにたとえた。『万葉集』によると、家持は、独(ひと)り天漢(あまのかわ)をふり仰いで心に思うところをうたったのだという。詠作は天平十年(七三八年)、二十歳の家持の歌である。七夕の歌は宴会でうたわれるのが通例であるところから、そうではない「独り」の七夕詠であると、ことわり書きを付記したのだろう。天平十年の七夕の宵に、天空のロマンスを想像しながら若い家持の心に去来していたのは、いったいどのような思いだったのだろうか。万葉の七夕の歌には、船出の時に雲や霧がたつとうたった歌が多い。
七夕の歌には作者のわからない歌も六〇首ほどあり、中国から伝来した七夕(チーシー)の風流が、一部の貴族や官人たちだけのものではなく、奈良の都にすむ多くの人々にも広がっていたことが知られる。その作者未詳の歌からあげてみよう。
このゆふべ降(ふ)り来(く)る雨は彦星(ひこぼし)の早漕(はやこ)ぐ船の櫂(かい)の散沫(ちり)かも
(巻十、二〇五二)
天の河霧立ちのぼる織女(たなばた)の雲の衣(ころも)の飄(かへ)る袖(そで)かも
(巻十、二〇六三)
雨や雲をうたい、それらを彦星の漕ぐ櫂のしずくや織女のひるがえる袖などに見立てる趣向は、万葉風というよりむしろ古今の歌風に近いが、このような七夕の歌が都のちまたで、さかんにうたわれていたのだろう。
河のほとりで神に捧げる衣を織り、おとずれた神を迎え結婚するたなばた姫の伝承と、中国にあった七月七日の夜に星を祭る風習が、いつの時代にひとつにとけあって、たなばたの祝祭となったかは、はっきりしない。たなばたの祭りが日本伝統の習俗になっていったように、中国でも七夕は年中行事のひとつとして、ずっと行われてきた。時代としてはすこし古いが、一八九九年に書かれた敦崇(とんすう)の『燕京歳時記(えんけいさいじき)』に「鵲の橋かけ」のことを記録している。これによると、七月七日のすがすがしい早朝は、鵲が(鴉(からす)も)飛んで来て鳴きはじめるのが、いつもよりはやや遅い、これは橋をかけに行くからだというのである。橋をかける鵲の苦労がしのばれようというものだ。
最後に、奈良時代の人々も読んでいたろう中国の詩集『玉台新詠集(ぎょくだいしんえいしゅう)』から、美しい七夕の漢詩をあげてみたい。「古詩十九首」と呼ばれる作品のなかの一首、作者は枚乗(ばいじょう)という漢代の人ともされているが、実際のところはよくわからない。
|
迢迢(てうてう)たり牽牛星(けんぎゅうせい) |
彦星ははるかかなたにあり |
|
皎皎(かうかう)たり河漢(かかん)の女(ぢょ) |
こちらには織り姫がかがやく |
|
繊繊(せんせん)として素手(そしょく)を擢(あ)げ |
織り姫はほっそりとした白い手で |
|
札札として機杼(きじょ)を弄(らう)す |
さっさっと音をたてながら機(はた)のひをはしらせる |
|
終日(しゅうじつ) 章(しやう)を成(な)さず |
ひねもす織りつづけても 織物の綾(あや)をなさず |
|
泣涕(きふてい) 零(お)つること雨のごとし |
涙はこぼれて雨のよう |
|
相去(あいさ)ること復幾許(またいくばく)ぞ |
それほど隔(へだ)てられているものでもないのに |
|
盈盈(えいえい)たり一水の間(あひだ) |
水をたたえたひとすじの河の むこうとこちら |
|
脉脉(ばくばく)として語(かた)るを得(え)ず |
じっと見交わすだけで ことばをかわすこともできない |
|
中国の詩集『玉台新詠集(ぎょくだいしんえいしゅう)』 |
福岡女学院大学教授 東 茂美
(日本古代文学 日中比較文学)